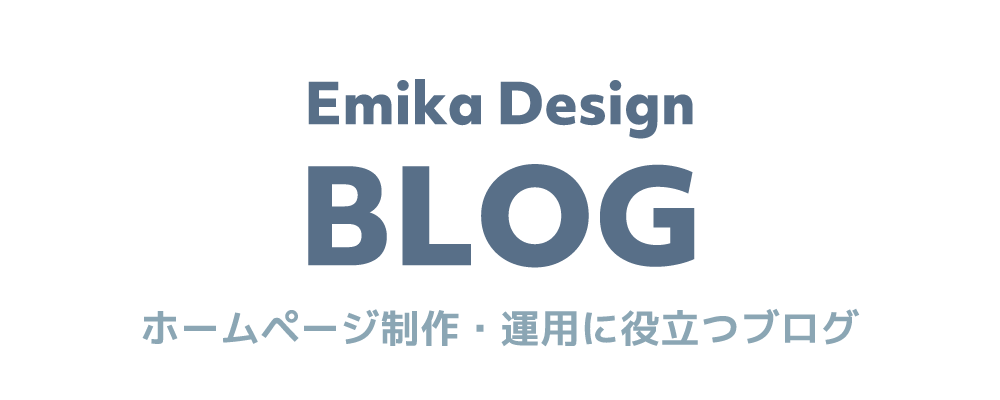今回は集客導線設計の参考にしている本を紹介します!
読んだのはこの本!
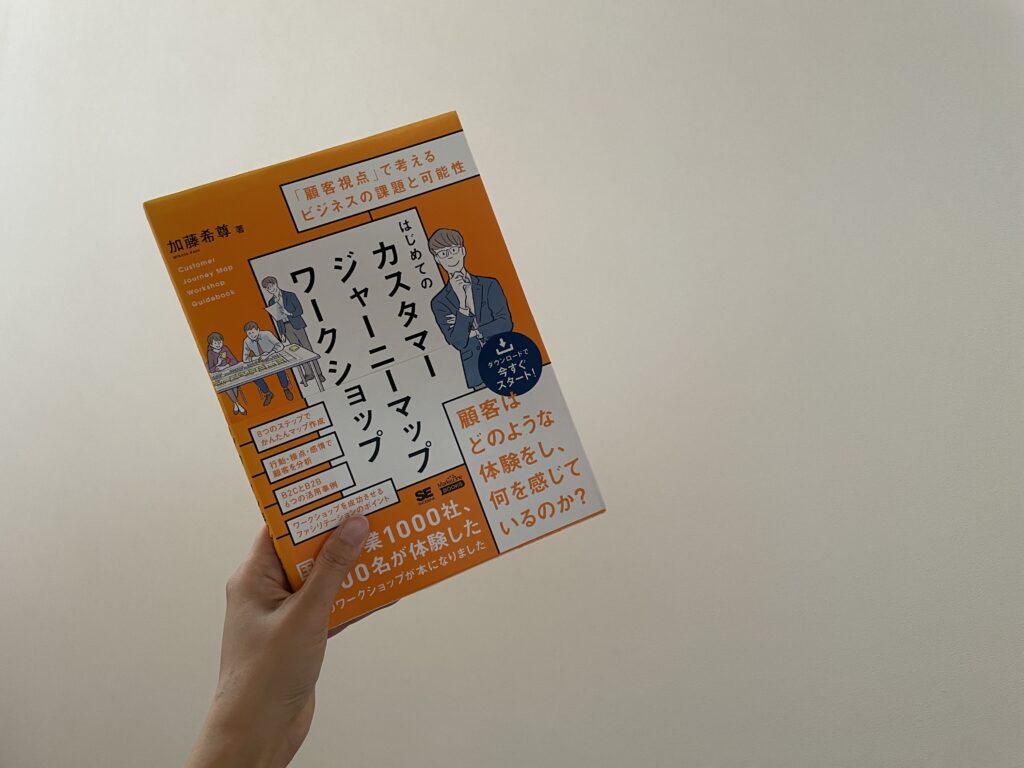
本の概要
この本は、カスタマージャーニーを作るワークショップを社内などで行うファシリテーター役の人向けです。
なので、カスタマージャーニーマップの作り方はもちろん、作り方の注意点や、説明の仕方など、ワークショップの進め方まで書いてくれています。
本から学んだこと
カスタマージャーニーマップとは?
カスタマージャーニーは、お客様の一連のブランド体験を「旅」に例えた言葉です。
一連のブランド体験とは、商品を認識したり、購入したり、再購入したりといった体験のことです。
カスタマージャーニーマップでは、これらの流れを時系列に並べて、お客様の行動やその時の感情を把握することで、より良い顧客体験にするための改善ができるというツールになっています。
「スコープ(虫めがね)」で注目することが大切
カスタマージャーニーマップで大切なのが、「スコープ(虫めがね)」で注目することです。
カスタマージャーニーマップを作る目的は、単に顧客体験を可視化するというものではありません。
目的は「成約率をUPしたい」「お申し込みを増やしたい」「なぜリピートにつながらないのか知りたい」というように、ビジネスのお悩みによって異なると思います。
ということは、一連の流れを大きく描いた地図だけでは、あまり改善につながらないということです。
大切なのは、お客様の行動の中で、どの部分に着目するか?ということです。
「キャンペーンに申し込むまでの流れ」「予約から来店までの流れ」「ページを見つけてからお問い合わせまでの流れ」など、改善に必要な部分に「スコープ(虫めがね)」を当てて、作成していきます。
つまり、テンプレ通りに、認知から購入までの流れを書き出すだけでは、いいカスタマージャーニーマップ(改善につながるもの)になりません。
「スコープ(虫めがね)」をどこに当てるか?を考えて作成してみましょう!
「入力情報」が「出力情報」の質を左右する
カスタマージャーニーマップを作る作業は、「入力」と「出力」のプロセスといえます。
「出力」は、「入力」を元に考えたお客様の行動や、感情、タッチポイント(接点)、改善策(施策やアイディアなど)です。
つまり、「入力情報」のクオリティが低いと、良い「出力情報」が出せないということです。
例えば、「ペルソナがずれていた」「スタート地点を誤った」ということが起こると、適切なカスタマージャーニーマップが作れず、結果改善しても見当違いになってしまう、ということです。
カスタマージャーニーマップを活用した改善で失敗しないためには?
目的を明確にしてから取り組む
「何のためにカスタマージャーニーマップを作るのか?」
「どの課題を改善したいからカスタマージャーニーマップを作るのか?」
これらを明確にしてからでないと、正確なカスタマージャーニーマップは作れないと言えます。
スコープ(虫めがね)をどこに当てるか決める
解決したい課題から考えて、お客様の行動のどの部分にスコープを当てるのか?を決めましょう!
ペルソナを明確にする
ペルソナは、明確であればあるほど、精度があがります。
例えば、ペルソナの平日の過ごし方、休日の過ごし方、お金の使い方、支払いに関する価値観、家族構成、居住地、年収、などです。
さまざまな要因から、ペルソナの考え方や行動が変わるので、できるだけ明確にすることが大切です。
今回紹介した本はこちら↓